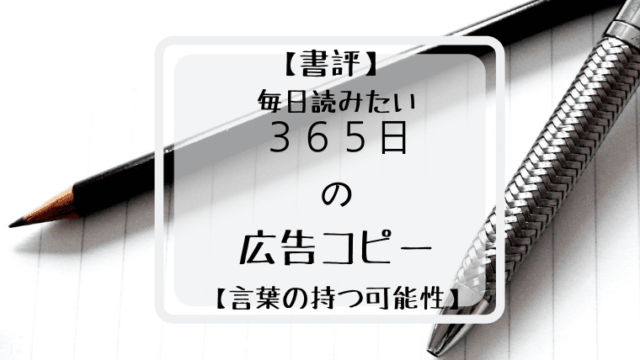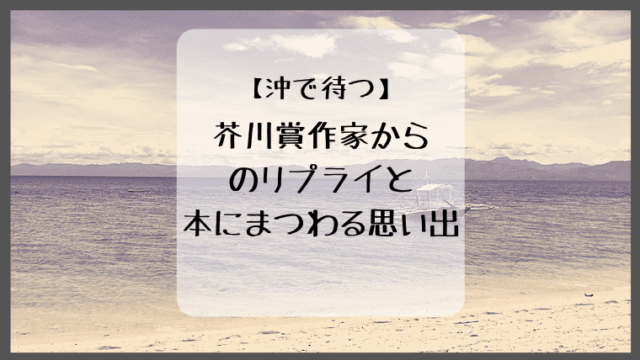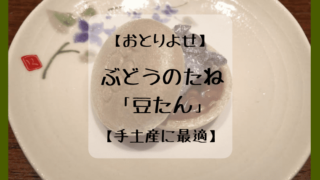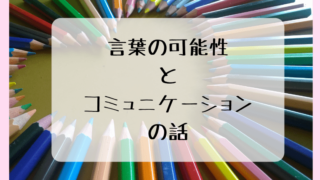「これは今の私が読むべき本だ」
この本を手に取ったのは、そんな変な使命感からです。
出産してからずっと本なんか読んでいなかったのに、偶然友人がSNSで紹介していてこの本のことを知りました。
おそらく彼がこの小説について言及していなければ、私は「キム・ジヨン」に出会うことはなかったと思います。
本屋へ行ったとしても絵本コーナーだけを見て帰る私が『82年生まれ、キム・ジヨン』に出会ったのは、偶然の出来事でした。
本を読み終わって残ったのは、ヒリヒリとしたなんとも言えない胸の痛みと、かすかな安堵感でした。
本文にはネタバレも含んでいますので、ご注意ください。
『82年生まれ、キム・ジヨン』について
ある日突然、自分の母親や友人の人格が憑依したかの様子のキム・ジヨン。誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児……彼女の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるものが浮かびあがる。筑摩書房「82年生まれ、キムジヨン」特設ページより
2016年に韓国でこの小説が発行されるとたちまちベストセラーとなり、社会的な動きへと発展していきました。
「キム・ジヨン」という1人の女性を通して見る社会構造。
女性であることで受ける差別や理不尽な扱いについて、彼女の半生を通して、それは非日常ではないことをみてとることができます。
家庭では弟が大切に扱われ、学校へ行けば男女の不公平な扱いに直面します。
出席番号が男子の方が早いことや男子の服装規定がゆるいこと。それは、1つ1つ見れば些細なことかもしれません。
けれども、番号の遅い女子は狭いランチルームでは後から席につかなくてはなりません。時間内に食べ終わらないという理由で先生に叱られる大部分は女子なのです。
古い公立中学では「男子はよく動くから」スニーカーでも革靴でもいいのです。女の子は革靴を徹底されて、寒い冬でも黒のストッキング。
社会に出ても、そんな「些細なこと」の繰り返しです。
韓国で多くの女性が共感したというこの小説。
文化や政治的背景は異なるものの、その理由がわかる女性は多いはずです。
女性であることの息苦しさ
 男女の差に関して言えば、韓国には朝鮮戦争や徴兵制という日本とは異なる社会的背景があります。
男女の差に関して言えば、韓国には朝鮮戦争や徴兵制という日本とは異なる社会的背景があります。
でもそれが男女の不公平さを許す免罪符にはなりません。
理不尽な扱いを受けながらも、たくましく生きるキム・ジヨンの母。
これまでの些細な出来事が積み重なって、産後ついに精神のバランスを崩してしまうキム・ジヨン。
母世代を見習うべきだとは思いません。
情報が多い昨今では、キム・ジヨンが精神科へ足を運ばざるを得なくなったのは当然のように感じます。
「おかしいこと」を「おかしい」と感じる心は、時として生きることを困難にし、それはふっと力を抜けば転落してしまいそうな危うさも含んでいるのです。
印象的なキム・ジヨンの言葉
 キム・ジヨンは結婚し、周囲からは当然のように子どもはまだかと急かされます。
キム・ジヨンは結婚し、周囲からは当然のように子どもはまだかと急かされます。
簡単に「子どもを持とうよ」という夫。
「僕もちゃんと手伝うからさ」
「最悪、君が会社を辞めることになったとしても心配しないで」
この小説が多くの共感を集めたのは、こういった会話のリアリティでしょう。
夫に返したキム・ジヨンの言葉にせつなくなったのは、私が結婚・妊娠・出産のたびにいろいろなものを失ってきたからなのかもしれません。
母性愛は宗教なんだろうか。
天国は母性愛を信じるもののそばにあるのか。
社会に出て、結婚し、妊娠出産で家庭に入ること。
特になんとも思わない人もいるかもしれません。
私は、キム・ジヨンと同じように出産前に仕事を手放し、女の子を出産し、一児の母となりました。
キム・ジヨンが葛藤するたびにヒリヒリとした胸の痛みを感じずにはいられませんでした。
81年生まれの私
「女の子なんだから」に感じる違和感
私はキム・ジヨンと1つ違いです。
彼女ほど女性であることによる差別を受けてきたわけではありません。
でも育ってきた中で、幾度となく、「女なんだから」と言われてきました。
「女の子なんだから」「女性らしく」
その言葉を聞くたびに反発したくなり、いつも「男の人に負けないように」と躍起になっていました。
男性の多い営業職を選んだのも、「男性に負けたくない」という気持ちが少なからずあったからです。
たくましさの裏の感情
営業時代、得意先との接待には、上司がついてくることが暗黙の了解になっていました。トラブル防止のための対応策でした。
それでもときどき得意先からのセクハラ話は耳にしました。それは珍しいことではなく、私も何度かそんな経験をしました。業界内で、少しずつ女性営業が増えていたほんの10年前の話です。
会社全体では全国で600人以上いる営業職の中で、女性は20〜30人程度。
女性の先輩たちは、結婚や出産のためにほとんどが会社を去っていきました。
営業成績が良かった先輩も後輩指導のうまい優しい先輩もみんな辞めていきました。先輩たちは、会社を離れた後に母になったと風の噂で聞きました。
男性と同じように働こうとしても見えない壁があり、そのたびにぐっと踏ん張るか、黙って去るしかなかったのです。
キム・ジヨンを通して感じること
 この小説は男性と女性で、感じ方が異なると思います。
この小説は男性と女性で、感じ方が異なると思います。
男性の中には「大げさな」と思う人がいるかもしれません。
「女だからこその特権もあるはずだ」と感じる人もいるのではないでしょうか。
私は女性としてこの小説に共感できたし、どうしようもできない現実を前に、ただ立ち尽くすしかない気持ちもよくわかりました。
できれば、私はこの小説を1人でも多くの男性に読んでほしいし、読み終わったあとにどんなことを感じるのか直接聞いてみたいです。
彼らの声を聞いたら、今まで抱えていた苦しみから少しだけ解放されるのではないかという期待が、少なからずあります。
それはこの小説を読んだ1人の女性としての切実な願いでもあります。
さいごに
この記事のタイトルを「共感」とか「涙」という言葉ではなく、「安堵感」という言葉を選んだ理由。
それはこれまで感じていたことを、この本に代弁してもらえたという気持ちからです。
女性であることの苦しさを声に出していいのかもしれないと思えたのはこの小説のおかげです。
大好きな仕事を手放した私は、小説の中の1節が痛いほどよくわかりました。
サラリーマンの疲労も憂鬱さもしんどさもよく理解しているけれど、それでもなぜか羨ましくて、しばらくそちらの方を見てしまった。
毎日の育児に追われ、社会から取り残されていくような感覚に陥いる中で、この小説に出会えたことは幸運なことだと今は思います。