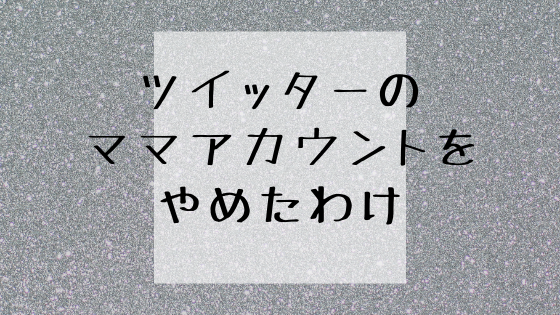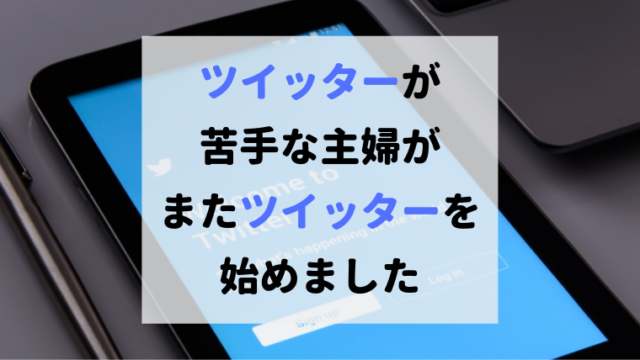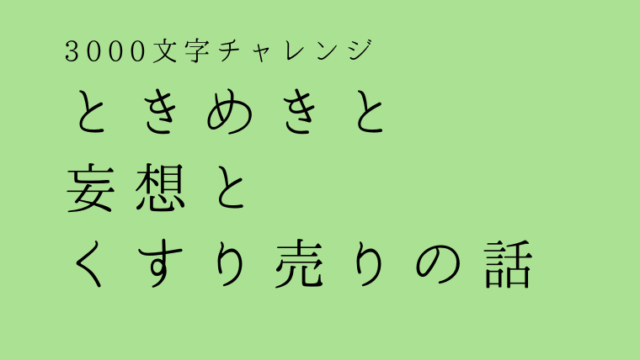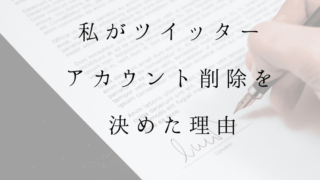9月27日 東京高等裁判所 725号法廷
事件名 殺人等
走り書きした手書きメモ。
つぶらな瞳で見つめる犬の絵が描かれたメモ帳には似つかわしくない言葉が並ぶ。
被告人はニュースで聞いたことのある人物だ。
法廷でその男が語る言葉を必死にメモをとる。
事件の核心に迫る言葉を聞き漏らさないよう走り書きをしていた。
その年の夏休みの課題は「裁判を3つ傍聴してレポートを書きなさい」というものだった。
経営学部にもかかわらず法学部の講義を選択していて、しかもいつも大教室の前の方で授業を聴いていた。
別に法律関係の仕事につきたかったわけではない。
ただなんとなくその授業を選んだ。
レポート課題を聞いたとき正直ちょっとめんどくさいと思った。
裁判なんてもちろん見たことはないしテレビの世界でしか知らない。
今思えば、夏の暑い日に3回も裁判所に足を運ばなくてはいけないのが憂鬱だっただけなのかもしれない。
傍聴する裁判は事前に調べず裁判所に到着してから決めることにした。
偶然にもニュースで何度も耳にした事件の裁判の予定を目にした。毎日毎日ニュースで繰り返し報道されていた事件。
あの事件に関わった人間の裁判を思いがけず傍聴することになり少し緊張していた。
目の前に現れたその男は色白でやせ細っていた。
事件に対して語るその姿は日本中を震撼させた事件を起こした人間には見えない。
神経質でまじめそうだった。
そして「普通」の人に見えた。
数年後、森達也のドキュメンタリー映画「A」を知った。
オウム真理教内部に潜入し撮影されたドキュメンタリーで、森が撮影していた当時、マスコミでは教団について何度も報道されていた。
教団内部での信者の生活とともに、教団の中から公安やマスコミの世界を映画では映し出していた。
信者=悪といった図式で多くのマスコミが報道する中、この映画に出てくる信者はみな「普通」の人間。
いや、そもそも「普通」って何なのか。
それすらわからなくなった。
白か黒か。
正義か悪か。
世の中はそんなに単純じゃないはずなのに世界はその2つで埋め尽くされていた。
森達也の描く世界は白か黒の2色で染まった世界ではなく、でもきれいなカラフルな世界でもない。
この世界には言葉で表現できない色があることを私に教えてくれた。
「A」撮影日誌の中で森はこう書いている。
「一人ひとりはすべて違う。
皆それぞれの事情や過去を背負いながら、必死に毎日を生きている。
大事なことだ。誰もが懸命なのだ。
誰もが必死なのに、どこかで何かがくい違い、
何かが短絡し何かが過剰になって、
そして皆傷つけあっている」 (「A」撮影日誌 森達也著)
映画鑑賞後、あの夏の法廷でとったメモを読み返してみた。
「最初に入信した時、人類救済という目的があった」
「人が幸せになれるようにという目的あった」
「救済という理念は正しかったと思うが自分のとらえ方が間違っていた」
下宿先に入っていた1枚のチラシで運命が変わってしまった青年。
彼は懸命にそして必死に生きていた。
いずれ死刑判決が下りることも知らずに。
数年前、森達也の著書「死刑」を読んだ。
ちょうど福祉の資格を取るために専門学校に通っていて、レポートの課題図書としてこの本の名前があがっていた。
ここにそのとき書いたものを掲載したいと思う。
「想像を停止すること」 『死刑』森達也 を読んで
「知らないことを自覚するためには、知らない何かへの想像力が必要だ。
死刑にはその想像力が働かない。」(本書より引用)
マスコミから流される犯罪報道。
「善と悪」という単純な構造で、視聴者を煽る。
いつしか私たちは、被害者の感情を想像した気になって、加害者は悪であるという決めつけを行う。
想像は停止している。民意で死刑が成り立っていることの現実だ。
著者の森が多くの日本人と異なる点は、何人かの確定死刑囚と関わりがあるということだ。
彼は死刑廃止の考えを持ちながらも、それをはっきりと口に出すことはしていない。
この本がノンフィクションであるという特性もあるだろうが、それ以上に森自身が死刑廃止を訴える確固たる理由が見つからずに悩んでいるように見えた。
ベールに包まれた「死刑」を様々な角度から見つめ、想像することでこの国の死刑を紐解いていこうとする。
そして死刑廃止派・存置派と対面し、目に見えぬ死刑の現場を想像しながら、森は結論を出す。
「これが僕の結論。(中略)僕は人に絶望したくない。生きる価値のない人など認めない」
「僕は彼を死なせたくない」
確定死刑囚とのやりとりで出した結論。
非論理的で、感情的。
結局、人への情や思いが死刑廃止へと傾かせるのかもしれない。
この本で語られるように、人を殺したからと言って、殺されて当然という根拠などどこにもない。
私たちに殺す権利もない。
身近な人間が死刑を宣告されたとする。
それを想像することは可能だ。
まもなく絞首台に連れて行かれる。胸が引き裂かれそうになる。
それがもし、見知らぬ人間であったら。
私には犯罪加害者を想像し、死刑廃止を叫ぶほどの強い思いはない。
ただ想像を停止せずに生きていこうと思う。
想像力をとめることは、人を殺すことだから。
このレポートを提出した当時、被告人はまだ死刑執行がされていない。
これについて議論するほどの知識を私は持っていないので、死刑について賛成とも反対とも言えない。
ただ自分の大切な人が被害者となったらその気持ちはどちらかに大きく傾くかもしれない。
そしてもし自分の大切な人が加害者になったとしたら・・・
あの夏の暑い日、東京高裁で裁判を傍聴して
そしてドキュメンタリー映画「A」を観て
森達也の著書を読んで
そして私が傍聴した裁判の被告人の死刑が執行されて
この世界は白と黒では表せないのだという思いが強くなった。
先日、友人がツイッターでこんなことをつぶやいていた。
「嫌なやつ」とか「悪いやつ」はいなくならないが、「悪いことをしてやろう」と思ってやっている人はなかなかいない。
ではなぜ他人にとって「嫌なやつ」「悪いやつ」になってしまうのかというと、人によって正義が違うからである。
悪人は悪人なりに「正しいこと」をしているつもりなんである。
「映画」をテーマにした記事でドキュメンタリー映画「A」を選んだのはこの言葉がきっかけだった。
友人の言葉を借りれば、教団幹部にとってあの事件は「正義」だったのかもしれない。
そしてその「正義」はとても悲しくて残酷なものだった。
世界が「白」か「黒」に染まるたび私はこの映画を思い出す。
誰も傷つけないなんてことは無理だけど、できるだけ想像を停止せずに
そして優しい色で世界を染めていけるように。
法律関係の仕事につくつもりはないと言っていたけれど
社会福祉士となった私は縁あって受刑者の福祉支援に携わることになった。
誰もが犯罪者になりたくて生まれてきたわけではない。
「誰もが懸命で、誰もが必死なのに、どこかで何かがくい違っていた」
目の前の受刑者と向かい合うたびこの言葉が浮かんでいた。
『世界はもっと豊かだし、人はもっと優しい』
私が好きな言葉で森達也の著書のタイトルでもあるこの言葉。
色彩豊かなカラフルな世界を望んでいるから今日も想像を停止せずに生きていこう。
別に正義感があるわけじゃない。ただ優しい世界で生きていたいだけ。
「あの偉い発明家も 凶悪な犯罪者も みんな昔子どもだってね」
イエモンのJAMを口ずさみながら今日もそんなことをとりとめもなく考えている。